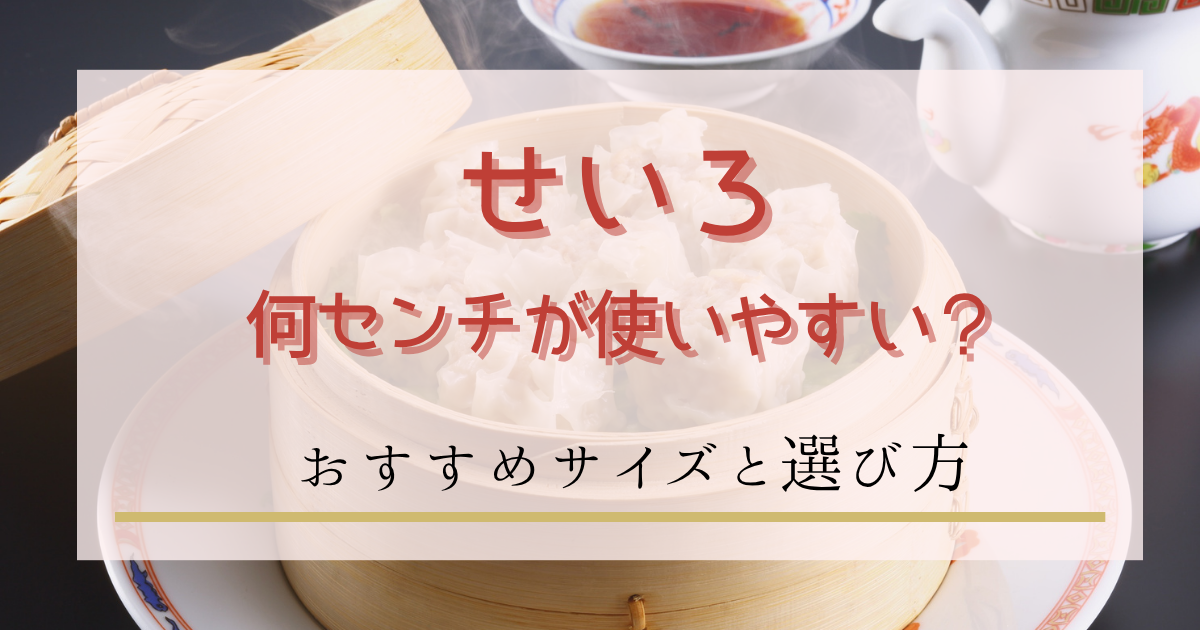せいろは何センチが使いやすいのか、気になりますよね。
サイズを間違えると、思ったより小さくて使いづらい・・鍋に合わなかったと後悔することもあります。
そこで、こんな悩みありませんか?
- 一人暮らしでどのサイズを買えばいいか分からない
- 家族で使うなら何センチがちょうどいいの?
- 鍋とせいろのサイズが合うか不安
- 大きいせいろは収納場所が心配
- 初心者におすすめのサイズを知りたい
このような疑問を解決していきます。
| 利用シーン | おすすめサイズ |
|---|---|
| 一人暮らしの方 | 15~18cmの小さめサイズ |
| 二人暮らしやカップル | 21cmがベスト |
| 3~4人家族 | 24cmを選べば万能 |
| 大人数や来客が多い家庭 | 27~30cmで本格的に |
| 初めて買う人 | まずは21~24cmの二段重ね |
さらに、本文で詳しく紹介していきますね。
せいろは何センチが使いやすい?サイズの目安
せいろは何センチが使いやすいか、そのサイズの目安について解説します。
それでは、サイズごとに詳しく解説していきますね。
①一人暮らしなら15~18cm
一人暮らしでせいろを使うなら、15cmから18cm程度の小さめサイズがおすすめです。
このサイズだと、ごはん茶碗1杯分の蒸しご飯や、小ぶりの肉まん、冷凍餃子などを蒸すのにちょうどいい大きさです。
小さめサイズは洗いやすく、収納も省スペースで済むので、キッチンが狭い一人暮らしの方にはありがたいですよね。
ただし、小さい分だけ一度に蒸せる量は限られるので、食べる量が多い方や作り置きをしたい方には物足りなく感じることもあります。
お試しでせいろ生活を始めたい人には、まずはこのサイズから入ると失敗しにくいです。
②二人暮らしなら21cm前後
二人暮らしの場合、21cm前後のせいろがちょうどよいサイズ感になります。
21cmだと肉まんなら4個程度、餃子なら12個前後が一度に蒸せるので、二人分の夕食やおつまみにぴったりなんですよ。
また、21cmサイズは家庭用の鍋にも合いやすい大きさなので、使い勝手がいいんです。
二人暮らしでたまにせいろを使いたいなくらいの方なら、まずこの21cmサイズを選べば間違いないです。
③家族用なら24~27cm
3人以上の家族なら、24~27cmのせいろが活躍します。
このサイズになると、肉まんなら6個前後、餃子なら20個以上が一気に蒸せます。
家族で一度に食卓を囲むときに便利なんですよ。
特に24cmは、家庭で一番使いやすい定番サイズと言われることが多く、購入する人が一番多い印象です。
27cm以上になると、大きめの魚を丸ごと蒸したり、野菜をたっぷり蒸したりできるので、料理の幅も広がります。
ただし、収納スペースはそれなりに必要になるので、キッチンが狭い場合は少し悩むところかもしれません。
個人的には、もし家族で食卓を楽しむ予定があるなら、思い切って24cm以上を選んだ方が後悔は少ないと思います。
④大人数や来客用は30cm以上
来客が多い家庭や大人数で食卓を囲むことが多い方には、30cm以上の大きなせいろがぴったりです。
このサイズなら、点心パーティーやホームパーティーでも大活躍。
大量の肉まんや野菜を一気に蒸せるので、料理の進行がスムーズになります。
ただし、30cmを超えると家庭用の鍋に合わないことも多いので、専用の蒸し鍋を用意する必要が出てきます。
また、大きい分だけ重さも増すので、持ち運びや洗うときに少し手間がかかります。
せいろは何センチが使いやすい?サイズ選びで失敗しないコツ5つ
せいろのサイズ選びで失敗しないコツ5つを紹介します。
それでは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
①鍋の直径に合うかをチェック
せいろを選ぶときに最も大事なのが、家にある鍋に合うかどうかです。
せいろは基本的に鍋の上に乗せて使うので、鍋の直径よりも1~2cm小さいサイズを選ぶ必要があります。
家の鍋が24cmなら、22cmか21cmのせいろがフィットしやすい。
鍋とせいろのサイズが合わないと、蒸気が逃げてうまく蒸せなかったり、せいろがグラついて危険なこともあります。
もしどうしても合う鍋がない場合は、せいろ専用の鍋(中華鍋や蒸し鍋)を用意するのも一つの方法。
肉まんを蒸したいなら直径が10cm以上は必要ですし、茶碗蒸しやプリンなら小さめのせいろでも十分ですよ。
魚を丸ごと蒸したい場合や、大きめの野菜をそのまま蒸したい場合は、24cm以上がないと入らないこともあります。
せいろの内径を考えて、蒸したい食材がちゃんと収まるかを想像してみてくださいね。
③収納場所を考える
せいろは使っていないときに重ねて収納できますが、それでも直径24cm以上になると、キッチンの棚をかなり占領します。
特に一人暮らしや狭めのキッチンの場合は、18cmや21cmくらいが収まりやすいです。
逆に広いキッチンや棚がしっかりある家庭なら、27cmや30cmを置いても問題ないですよね。
収納スペースがなくて出しっぱなしになると、せいろが乾きにくくなったりカビやすくなったりするので、保管も含めてサイズ選びを考えてくださいね。
④重ねて使う場合の安定性
せいろは一段だけでなく、二段や三段に重ねて使えるのも魅力ですよね。
ただし、大きいサイズを重ねると持ち上げるときにグラついたり重くなったりするので注意が必要です。
21cmや24cmなら二段重ねも扱いやすいですが、30cmを三段重ねにすると本当にズッシリきます。
せいろを頻繁に重ねて使いたい人は、サイズだけでなく「重ねやすさ」「安定性」もチェックすると良いですよ。
⑤持ち運びやすさも意識する
せいろは意外と軽いですが、大きくなるほど持ち運びが不便になります。
特に蒸した直後は中がアツアツなので、持ちやすさってかなり大事なんです。
小さめのせいろは片手でも扱えますが、27cm以上になると両手でしっかり支えないと危ないです。
また、洗ったあとに乾かすときも、大きいせいろは場所を取るし重さもあるので、意外と扱いにくいんですよね。
そのため、普段の生活でどれくらいの大きさならラクに持てるかを想像しながら選んでみてください。
せいろは何センチが使いやすい?サイズ別メリットとデメリット
せいろのサイズ別メリットとデメリットについて解説します。
それではサイズごとに詳しく見ていきましょう。
①小さいせいろのメリット・デメリット
最大のメリットは「手軽さ」です。
軽くて洗いやすく、収納もラクなので、キッチンが狭くても問題なく使えます。
また、蒸す時間が短く済むのもポイント。
小さめの野菜や冷凍食品を温めるだけなら、あっという間に完成します。
ただし、デメリットもあります。
一度に作れる量が少ないため、大食いの人やまとめて調理したい人には物足りません。
また、大きな肉まんや魚などは入らないことも多く、料理の幅が少し狭くなるのが難点です。
②中くらいのせいろのメリット・デメリット
メリットは「バランスの良さ」です。
一度に蒸せる量が十分で、家族用の食卓でも活躍。
21cmは二人暮らしに最適、24cmは3〜4人家族でも使える万能サイズと言われています。
さらに、鍋に合いやすいサイズなので、専用鍋を買わなくても家にある鍋で対応できるケースが多いのも嬉しい点です。
一方で、デメリットは収納スペースを少し取ること。
18cmに比べると大きさも重さも増えるので、狭いキッチンだと少し圧迫感があります。
ただし、料理の幅と日常使いのしやすさを考えると、中サイズは一番失敗しにくい選択肢です。
③大きいせいろのメリット・デメリット
メリットは、一度に大量に作れること。
肉まんなら10個以上、餃子なら30個以上を一気に蒸せるので、料理がとてもスムーズになります。
また、大きな魚や野菜をそのまま蒸せるため、豪華な料理やおもてなし料理にも映えます。
ただし、デメリットは取り扱いの大変さです。
重くて洗いにくく、収納スペースも大きく必要。
さらに、30cm以上のせいろは家庭用の鍋に合わないことが多く、専用の蒸し鍋を用意しなければならないケースもあります。
毎日使うというよりは、特別なシーンで活躍するイメージでしょう。
せいろは何センチが使いやすい?料理別おすすめサイズ
せいろの料理別おすすめサイズについて解説します。
料理によってせいろのベストサイズは変わります。
ここでは具体的に見ていきましょう。
①肉まん・点心にぴったりのサイズ
肉まんや点心を蒸すなら、21cm〜24cmのせいろが一番バランスよく使えます。
21cmなら肉まんが4個、24cmなら6個程度並べられるので、二人暮らしや家族でも十分満足できる量です。
また、シュウマイや小籠包などの点心はサイズが小さいので、21cmでも10個前後を一気に蒸すことができます。
せいろで蒸した点心は余分な油が落ちてヘルシーで、ふんわりと仕上がるので一度食べたら普通の蒸し器には戻れない!と感じる人も多いです。
②野菜や魚を蒸すならこのサイズ
野菜や魚を蒸したい場合は、24cm以上のせいろが活躍。
特にキャベツやブロッコリー、サツマイモなどの大きめ野菜は、18cmや21cmだと入りきらないことも多いです。
魚も切り身なら小さいせいろでOKですが、一尾丸ごと蒸したい場合は27cm以上必要になります。
野菜をたっぷり蒸して作り置きしたい方や、魚料理をよくする方には24cm以上をおすすめします。
③茶碗蒸しやプリン用のサイズ
茶碗蒸しやプリンなど、器ごと蒸す料理には18cm〜21cmくらいがちょうどいいです。
小さめのせいろなら茶碗蒸しを2個〜3個並べられるので、家庭のおやつや夕食の副菜にぴったり。
また、プリンやカスタードを蒸す場合は、温度管理がしやすい小ぶりサイズのせいろが扱いやすいですよ。
器を並べやすく、蒸気が均等に回るので失敗が少なく、なめらかな仕上がりになります。
④おもてなし料理に向くサイズ
ホームパーティーや来客用には、27cm以上のせいろが華やかです。
大量の点心や野菜を一気に出せるので、調理もラクになりますし、見た目の迫力も抜群。
ただし、持ち運びや洗い物が大変になるので、普段使いには不向きかもしれません。
せいろは何センチが使いやすい?初心者が最初に買うべきせいろの選び方
初心者が最初に買うべきせいろの選び方について解説します。
はじめてせいろを買うときは、「サイズ」「段数」「素材」「購入方法」を意識すると失敗しません。
順番に見ていきましょう。
①最初は21~24cmが無難
21cmは二人暮らしや一人でたっぷり食べたい人にちょうどよく、24cmは家族用や幅広く使いたい人に最適です。
小さいせいろは手軽ですが容量不足になりやすく、大きいせいろは扱いにくいため、バランスの取れた21〜24cmが一番無難。
実際、せいろを初めて買う人の多くが21cmか24cmを選んで「これで正解だった!」と感じています。
②二段重ねが便利
せいろは一段でも使えますが、初心者には二段重ねが断然おすすめです。
二段あれば、一度にご飯とおかずを同時に蒸したり、点心と野菜を一緒に用意できたりと効率的。
また、二段をバラして一段だけで使うこともできるので、用途に合わせて使い分けられるのも便利ですよ。
一段しかないともっと蒸したいのに入らない!と後悔するケースも多いので、最初から二段を買っておくと失敗が少ないでしょう。
③竹製と檜製の違い
せいろには大きく分けて竹製と檜製(ひのき製)があります。
竹製のせいろは価格が手頃で、軽くて扱いやすいのが特徴。
見た目も中華料理店で使われるような雰囲気があり、手軽に楽しめます。
檜製のせいろは高級感があり、香りが食材にほんのり移るので、より上品な仕上がりになります。
耐久性も高く、長く使えるのが魅力です。
初心者にはまず竹製がおすすめですが、「長く使いたい」「香りも楽しみたい」という方は檜製を選んでも良いと思います。
④おすすめのセット購入方法
せいろを初めて買うときは、「せいろ本体+フタ+鍋」がセットになったものを購入すると安心。
単品で買うと「鍋に合わなかった!」という失敗が起きやすいのですが、セットなら最初から相性バッチリで使えます。
特にネット通販では「せいろ+専用鍋+蒸し布」がセットになった商品が多く、初心者には最適ですよ。
また、二段重ねが最初からセットになっている商品を選ぶと、料理の幅が一気に広がります。
| 購入スタイル | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 単品購入 | 必要なものだけ揃えられる、安価に始められる | サイズが合わないリスク、追加購入が必要になる場合あり |
| セット購入 | 最初から相性が保証されている、初心者でも安心 | 価格がやや高め、不要なものもついてくる場合あり |
まとめ|せいろは人数と料理に合わせてサイズを選ぶのが正解
せいろのサイズ選びは、「何人で使うか」「どんな料理を作るか」によって決めるのがベストです。
一人暮らしなら15~18cmで十分ですが、二人暮らしなら21cm、家族なら24cm以上を選ぶと使いやすさが格段に上がります。
大人数や来客が多い家庭では27~30cmが活躍しますが、その分収納や取り扱いに注意が必要です。
また、初心者ならまず21~24cmの二段重ねを選んでおけば、料理の幅が広がり失敗も少ないですよ。
人数や料理スタイルに合わせてサイズを選べば、せいろは毎日の食卓をぐっと豊かにしてくれます。